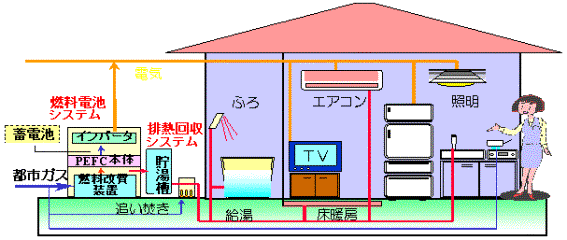
電力自由化政策
電力自由化政策
No.6 燃料電池の時代=水素エネルギーの時代
水(H2O)を電気分解を水素と酸素に分解されます。これと逆に燃料の水素を酸素と科学反応させて電気を起こすのが燃料電池車です。エネルギー効率はエンジン車の2倍、電気は騒音なしに発生し、排出されるのは水だけ。そのため究極のクリーンエネルギーといわれています。
この車載用は、各自動車メーカーが何から水素を取り出すかにつき、しのぎをけずっています。ダイムラークライスラーやフォードはメタノール方式、トヨタやGMはガソリン改質、BMWとホンダは最終的には水素がメーンになると水素方式を重視しています。現在、ガソリン車のためのスタンドは日本中、世界中に整備されていますが、水素スタンドは未整備なので燃料を何にするかは大問題です。
もうひとつは定置用と呼ばれる家庭用1㌔㍗程度の小型燃料電池です。燃料電池を使った家庭はこんなイメージになります。
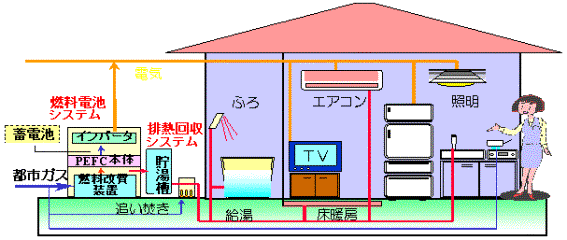
(出所)大阪ガスHP http://www.osakagas.co.jp/rd/sheet/026i2.gif
家庭用の燃料電池が普及すると送電線がいらなくなります。従って、陸の孤島やほとんど人の住んでいない地区に対する供給責任の態様もかわります。エネルギー産業も様変わりするだろうと予測されています。世界規模では送電線につながっていない人々は20億人いるそうです。
水素は二次エネルギーなので、問題は何から水素を作るかという点と普及のためのコストダウンが大問題です。定置用は天然ガスを使うことでほぼ決まりです。車の普及のためには価格を1/100にする必要がありますが、家庭用は1/10ですから定置用の方が普及は早そうです。
送電線の必要がない、天然ガスを使った家庭用発電機は分散型電源の切り札です。今後は電力、ガス、石油の業界間の垣根は低くなり、いずれエネルギーは水素と電力の供給に集約していくとみられています。
「太陽光や水力、風力といった再生可能エネルギーを使って水から水素を取り出し、水素輸送タンカーでエネルギー消費地に運ぶ」というのが経済産業省が「WE-NET計画」で描く21世紀後半の水素エネルギー社会の姿です。
アイスランドという地図でしか知らない寒そうな国があります。アイスランドでは水素エネルギー導入に国として取り組み、強力な政治的なリーダーシップのもと、ロイヤル・ダッチ・シェルやダイムラー・クライスラーのような有力企業を巻き込んで、強力に押し進めたそうです。
水素をどこから供給し、どう輸送するかについてはエネルギー産業が深くかかわるので、アイスランドのように素早く対応はできませんが、遅かれ早かれ水素時代に移行するのは間違いないでしょうから、実現のための政策をたててほしいものです。